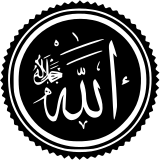|
クライシュ族
クライシュ族(英語:Quraysh, Quraish、アラビア語: قريش : Qurayš. "Quresh", "Quraysh", "Koreish", "Coreish"、トルコ語: Kureyş)は、4世紀頃からメッカ(マッカ)近郊を勢力圏として遊牧および交易を行っていたアラブ人の部族であり、イスラム教の創始者である預言者ムハンマドの出身部族として知られている。その一方でクライシュ族はムハンマドの布教活動を迫害し続けたイスラームの敵対者でもあり、クルアーンの中にもクライシュ族はしばしば登場する。その系譜は紀元前よりアラブ世界をカフターン族と二分していたアドナーン族にまで遡ることができ、アドナーン族はアラム人がアラブ化した民族であるとされている[1]。クライシュとはサメを意味するキルシュという語が元であり、他者を捕食するが自身が捕食されることはないサメの圧倒的な強さを指し示している[2]。現代においても、ヨルダン王国[3]やモロッコ王国[4]などではクライシュ族の末裔を国王としている。 ジャーヒリーヤ時代クライシュ族を含むアドナーン族の系譜はアダムにまで遡ることができるとされており、旧約聖書に登場するイシュマエルの長男ナビトの末裔であるアドナーンを祖としている。アドナーン族はアラビア半島の北部から西部、中央部を勢力圏として遊牧を行っていたアラム人の部族であり、アラブ化したアラブ族と呼ばれる。アドナーン族の主要な支族の一つであるムダル族のうち、預言者エリヤの孫フザイマの子であるアル=ナドル・ブン・キナーナを祖とするキナーナ族から分岐したのがクライシュ族であり、キナーナの曾孫であるフィフル・ブン・マーリク・ブン・アル=ナドル(クライシュ)がクライシュ族の直接の祖である。キナーナ族はアラビア半島の紅海沿岸地域(ヒジャーズ)に大きな勢力を持っており、その支族であったクライシュ族も4世紀頃にはヒジャーズ地方のメッカ周辺で遊牧生活を送っていたと考えられている[1][5][2]。 5世紀末、当時メッカおよびカアバ神殿を支配していたのはアラビア半島南部のイエメンからメッカに移住してきたカフターン族の支族であるフザーア族であったが、フザーア族の首長の娘婿となったクライシュ族のクサイイによって、フザーア族に代わりクライシュ族がメッカの支配権を獲得した。クサイイはムハンマドから見て5代前の祖先に当たり、クサイイが支配権を奪取したメッカにクライシュ族を呼び寄せ定住し始めたことによって、クライシュ族は部族集団としてまとまりを持ち始めたとされる[6]。その後もクライシュ族とフザーア族は同盟関係を継続しており、後の570年頃に起こったエチオピア軍によるメッカ侵攻の際には共同でエチオピア軍に対抗している[1]。カアバ神殿では偶像崇拝が行われており、当時の神殿の周囲には360におよぶ偶像が祭られていたとも言われている[7]。代表的な神としてアッラート、ウッザー、マナートなどの神々があり、クライシュ族は明けの明星の神であるウッザーを氏神にしていた[5]。クサイイの孫であり、ムハンマドの3代前の曽祖父に当たるハーシムの時代になると、サーサーン朝ペルシアと東ローマ帝国の抗争が激化し始め、アラビア半島においても沿岸地域の海洋ルートを中心に二大国が勢力を伸ばしていた[5]。そのような状況下においてハーシムはイエメンからメッカを経てシリアにいたる交易路を開拓し、冬にはインド洋航路によって東南アジアやインドからもたらされる香辛料をイエメンで仕入れメッカへと持ち帰り、夏にはメッカからシリア、地中海地域へと香辛料を運び地中海地域の特産品を仕入れるキャラバン交易を成功させメッカは発展していった。このような陸路による貿易においては通商路の安全確保が必要であったため、ハーシムは周辺のアラブ諸部族との間に盟約を結んでいき、メッカを中心とした緩やかな部族連合が形成されていった。また、ハーシムは交易ルートの支配権を確立するために、東ローマ帝国から商業特権を得たり、交易ルート上に位置するガザにも拠点を作ったりといった活動も行っており、このようなハーシムの貢献によってハーシムの一門(ハーシム家)はクライシュ族の中でも重要な位置を占める名門となっていった[5][8]。ハーシムの息子であるアブドウルムッタリブの時代の570年頃、東ローマ帝国の後援を受けたエチオピア軍がメッカに侵攻したが、軍事力に勝っていたにもかかわらずメッカに入城することなく壊走している。この戦いはムハンマドが生まれた年に起こったと考えられておりクルアーンの象章に取り上げられているが、エチオピア軍の壊走の理由としては神の奇跡の描写から天然痘の蔓延によるのではないかと考えられている[9]。またこのころ既にクライシュ族は上下関係ができており、メッカの中心部にすむ家柄の良い「谷間のクライシュ」と山腹に住む「外側のクライシュ」とに区別されていた。「谷間のクライシュ」はハーシム家、ウマイヤ家他合計12の氏族で構成された。 繁栄の一方で、メッカ内での貧富の差を生み出し部族としての連帯感が失われ、社会的矛盾をクライシュ族は抱えるようになる。これが預言者ムハンマドの誕生と新宗教イスラム教拡大の基盤になったと一般に言われるが、他方この交易はあくまで安い商品を運んだローカルなものであり、したがって一般に言われているような格差の開きに伴う価値観の変化はなかったと反論する声もある。 イスラム教との戦いムハンマドが啓示を受けまず身内のクライシュ族に布教を始めたとき、信者に成るものもいたが大多数のものは信仰しなかった。クライシュ族の多くは自分たちの既得権益を脅かし、多神教から一神教のイスラム教に改宗するよう説得するムハンマドに最初圧力をかけるだけだったが、クライシュ族が提示した妥協案をムハンマドが蹴ったことで本格的な迫害が始まる。619年ムハンマドの保護者だったアブー・ターリブが死亡し、弟のアブー・ラルブがその跡を継いでいた。アブー・ラルブはムハンマドの保護を取りやめ、ムハンマドは仕方なく信者達をエチオピアのキリスト教の国アクスム王国やヤスリブに脱出させなければならなかった(ヒジュラ)。 ヤスリブで信徒を増やし力を蓄えたムハンマドは、624年3月クライシュ族の隊商を襲撃した。初めての戦いによるジハード(努力目標)である。クライシュ族はメッカから援軍を差し向け、両雄は紅海沿岸バドルの水場で戦った(バドルの戦い)。数で劣るムハンマドだったが、天使が味方したと言われるほどの圧倒的勝利を収める。 復讐を誓うクライシュ族は、指導者アブー・スフヤーンの元、625年3月ヤスリブに侵攻(ウフドの戦い)。最初ムハンマド側は有利に戦いを進めるが、途中から形勢は逆転。クライシュ族は辛くも勝利を収める。戦いの途中ムハンマド死亡の噂が流れ、ムスリム側が浮き足立ったことがクライシュ族に勝利を導いた。しかし実際はムハンマド殺害には至っていなかった。 627年クライシュ族はユダヤ教徒と手を組み3度目の戦いに挑むが、堅く守るムハンマド側を攻めきれず兵糧不足により撤退、ここに双方の立場は逆転する(ハンダクの戦い)。そして628年3月双方が「フダイビーヤの和議」に至るにあたって、クライシュ族からの改宗者は激増する。 630年1月ムハンマドは軍を率いてメッカを急襲。既にほとんど抵抗はなくメッカは陥落した。ムハンマドはカーバ神殿にあった多くの偶像を全て破壊、メッカはついにムスリムの土地となった。この後クライシュ族はイスラム世界の指導者的存在としてその発展に大きく寄与する。正統カリフ時代、ウマイヤ朝、アッバース朝とクライシュの血を引く者による支配が続くが、その後アラブ人の優位性は失われ、クライシュ族も次第に影響力を失っていく。 しかしその後も預言者ムハンマドの一族としてイスラーム世界の尊敬を集めた。 クライシュ族とカリフ預言者ムハンマドがクライシュ族であったことから、伝統的にムスリムの最高指導者であるカリフ(ハリーファ)はクライシュ族でなければならないという意見は根強い。とりわけシーア派はムハンマドの従兄弟・娘婿のアリーとその子孫のみが女系でも男系でもムハンマドに最も近縁であり、唯一ムスリムの指導者たる資格があると主張した。 対してスンナ派は初期カリフがクライシュ族内から互選で選ばれたことから、ムハンマドとの血縁の近さは必ずしも絶対的なものではないとし、クライシュ族であれば多少血縁が遠くても良いとする。そのためややムハンマドとは血縁が薄いウマイヤ朝、アッバース朝の統治を認めた。またスンナ派世界では後にはクライシュ族でなくともカリフを名乗るものが出始め、最終的にはトルコ人のオスマン家がカリフを称するに至ったため、クライシュ族の血の論理も崩壊したといえる。 著名なクライシュ族出身者一覧
系図太字は正統カリフ。
出典
参考文献
関連項目 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||